ついに、5月26日から日経新聞でも特集が組まれるようになった、ウェルビーイング。
このテーマは、何も企業でなくても学校やいろんなサークルとかでも参考になりそう。
いよいよ、「ウェルビーイング」という考え方が広まって、幸せ第一の世の中になるといいなぁ。
第1回「御社の社員は幸せですか、診断で「心を見える化」
記事の冒頭に、「先の見通せない時代に、古くて新しい価値観が経営者の間で合言葉となっている。幸せ(幸福、ウェルビーイング)だ。社員の幸福の「健康診断」をしたり、担当役員を配置したり。社員が幸せであれば、創造性や生産性も高いとする研究成果も増えてきた。幸福度ランキングで先進国の下位に沈む日本。あなたの会社の社員は幸せですか?――」となっている。
そう、「社員が幸せであれば」→「創造性や生産性も高い」こと。つまり企業にとって業績することがだんだん科学的に分かってきたのだ!
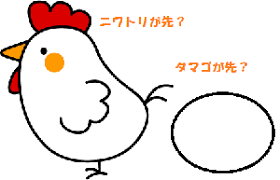
例えば、従来であれば「頑張って必死になって企業の業績がUPすれば、社員の待遇も良くなって幸せになる」という考え方が普通の世の中だったが、本当は逆で、「社員が幸せであれば、創造性や生産性も高くなるので、結果として企業業績はUPする」のが科学的に正しいと分かってきた。
これって、画期的な発見だと思う。鶏が先か卵が先かじゃないけど、本当は社員の幸せを追求していったほうが結果も良くなるということだ。
これは、学校でも一緒だろう。勉強することが子供にとって楽しく幸せなことであれば、自然と学力も向上していくはず。実際に幸福度ナンバーワンのフィンランドではそうした学校教育を行っている。
話しはそれたが、第1回の日経記事では、人間の幸せや不幸せを感じた時の血管収縮などに着目して、スマホでセンサーを感じる装置を開発した話など、心を「見える化」していることも紹介している。
3.5%の法則って?
これは、ハーバード大学(エリカ・チェノウェスさん)が提唱していて、「何らかの抗議活動に参加する人が人口の3.5%に達すると社会変革の転換点になる」という理論。
これでいくと、日本でウェルビーイングが普及するためには350万人まで広がることがポイントとのこと。ウェルビーイングが広まれば、働くことや勉強することが幸せになって、世の中もっと良くなると思う。
記事に出てた方々(ご参考)
- 積水ハウス(仲井嘉浩さん)
- はぴテック(太田雄介さん)
- 慶応大学(前野隆司さん)
- ハピネスプラネット(矢野和男さん)
- ハーバード大学(エリカ・チェノウェスさん)
さぁ。ウェルビーイングのはじまりはじまり!
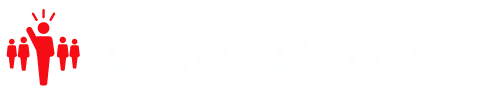



コメント