人はいろんな過ちを犯してしまうもの。
でも、自分を許せたら幸せだし、更に他人のことも許せたら幸せになる。この許すって言葉はどこからきているのだろうか調べてみたら興味深かった。
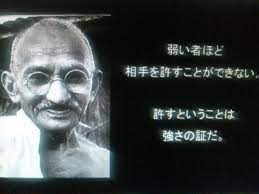
日本語と英語では若干ニュアンスが違う。
日本語の「許す」は、もともとは 「緩 くする」 と同義語で、<縛りを緩くする>ことが 「ゆるす」 だったそうだ。つまり、<相手が犯した行為に対する罰則や弁済の縛りを緩くしてあげる〉 という発想なのだそう。これが日本語の解釈。
英語の「許す」=「forgive」は、普通に読むと、
for =~のために
give = 与える
と思うのだが、forgiveの語源はラテン語の「Perdonare」(許す)からきていてforの意味が異なる。つまり
for = 完全に
give = 与える
という意味だそうだ。forgiveとは「完全に与える」ということ。
では、何を完全に与えるのか?
そもそも、forgiveとは、本来(悪いことをして)受けるべき罪を免除する、という意味のようだ。
つまり、悪いことをすることを許すのではなく、悪いことをしてしまった結果受けるべき罪を免除するということであり、悪いことをしても良いということではない。
それを踏まえると、先ほどのfor=完全に、give=与える、とはどういう意味か。何を完全に与えるのか?
私の解釈は、for・giveとは「私は(あなたは)悪いことしてしまった。だから当然罪を受けるべきだ。しかし、受けるべき罪を免除するから、これからは罪を犯さないようにしっかり生きていきなさい」という愛を・完全に・与えるメッセージではないかと思う。
許すこと。forgiveすること。
これも、ウェルビーイング!
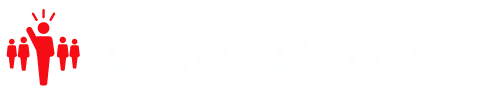
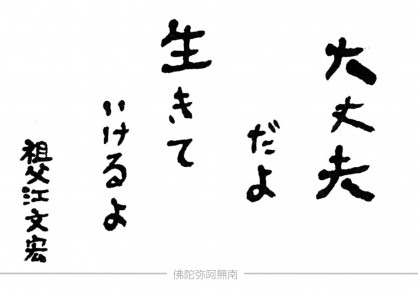


コメント