中津川浩章さんの「アートを通じたウェルビーイング」講演会に行ってきた。
中津川さんは、美術家・アートディレクターで、25年ほど前から障害がある人たちの表現活動のサポートに関わるようになり、社会とアートの関係性を問い直す活動に取り組んでいる。
障害のある方の表現活動において、クオリティの高い作品そのものが生む芸術的価値はもちろん大切だが、そして同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのは、もうひとつの言語としての価値とのこと。
また、この講演会で印象的だったのは、障害のある方のアートの話しのほかに、フィンランドにおけるアートの考え方だった。フィンランドは毎年「幸福度ランキング」で世界一の国だ。
自分たちの世界を良くするために使うのは「アート」だ

アートは自分の内面を表現すること。中津川さんは企業研修で「粘土を使って好きなものを作って下さい」と言うと、ほとんどの人は心に感じたものを作るのではなく、何か正しいものを作るようだ。
これは、子供のころから正しさを求められてきた教育のせいではないかと、中津川さんは言っていた。
日本人は人と違うことをすると避ける傾向があるのではないか。これまでの学校教育で、人と違ったことをすると笑われるのでは、とか馬鹿にされるのでは?と思って、本当の心の底にあるものを押さえつけているかも知れない。アートの哲学や価値を教えてきてもらってこなかった。
アートは、表現することで自分が自分らしくあることを許してくれる手段だろう。
「アール・ブリュット」という言葉も初めて知った。
「アール・ブリュット」
アール・ブリュットとは、既存の美術や文化潮流とは無縁の文脈によって制作された芸術作品の意味で、 英語ではアウトサイダー・アートと称されている。加工されていない生(き)の芸術、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側から湧きあがる衝動のままに表現した芸術である。フランスの画家ジャン・デュビュッフェ(Jean Dubuffet 1901-1985)によって考案されたことばである。
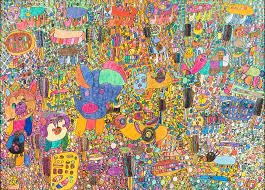
講演会の後に質問した。「日本の日常生活の中で、アートで豊かな世界を作るためにはどうすれば良いですか?」と。
中津川さんから、「例えば、詩を書いたり、絵を描いたり、音楽をやったりすることで、自分の内面を表現することでしょう」とコメント頂いた。
アートをこれまで意識したこと無かったが、これからもっと意識してみたいと思う。
これも、ウェルビーイング!
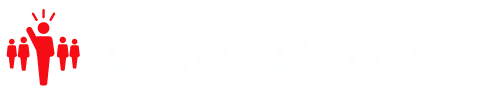



コメント
アートを生活に取り入れたいものです。