最近キラキラネームの話題が多い。
光宙と書いて、ぴかちゅう。
愛夜姫と書いて、あげは。とかもあるそうだ。
この手の議論であるあるは、「今どきの親は子供になんて変な名前をつけるのか」と苦言を呈することではないだろうか。
しかし、このキラキラネーム問題は、大昔からあった。
例えば、平安時代の第55代天皇である文徳天皇の女御であった「藤原明子」は、「ふじわらのあきらけいこ」と読むらしい。はぁ?である
また、本居宣長は「和子(かずこ)」という読み方はダメと言っている。
もともと「和」の訓読みは、なごむ、やわらぐであり、かずという読み方は存在しない。またかずは人名にだけ使われてきた。
そう考えると、キラキラネーム問題に対しては、別に大騒ぎする話しではない。
これから、100年後、200年後に名前がどうなっているかなんて分からないもの。
いま考えて変だと思うことは、昔の歴史を振り返ってみるとどうだろうか?と考えてみると冷静に対応できるものだ。
これって、何事も同様。今困ったとか悩むことがあれば、過去にもきっと誰かが同じ苦しみを抱えて乗り越えてきたことが見つかるかも知れない。
何が言いたいかというと、歴史を紐解いて調べると、いろんなことが分かるし、客観的に物事に対処できるということ。
これも、ウェルビーイング!
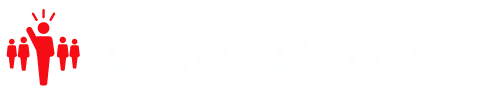



コメント