ボートの荒川選手がオリンピックに出場した。
学生時代のボート部は強い部ではあったけれど、最近はもっと強くなっている。
簡単に言うと、「自分たちは勝って当たり前」「先輩たちが強かったので、自分たちも同じ努力をすれば同じ目標を達成できる」という環境ができているからだと思う。
勝ち癖、負け癖という言葉もあるが、勝ち癖のある環境に身を置くことで、本来の実力以上の力も引き出されるのだろう。
こう考えると、高校野球の常連校や、東大合格常連校などは、もちろん指導者も含めて回りの仲間も同じ気持ちを持っているので、スポーツや勉強の分野で自分の実力以上のパフォーマンスを発揮できるのではないか。
こうした「環境」のことを考えてみると、「環境」=「その集団にいる人々の考え方」とするならば、「その集団にいる人々の考え方」とは「その人々の脳」から出ている「脳波=ミラーニューロン」の影響が大きいということかも知れない。
以前このブログで書いた「脳」のミラーニューロンも同じことを言っている。
「環境」とは、飛び交っているWiFiみたいなイメージ、かな。

例えて言うなら、WiFiが飛び交っている中で、自分の持っているスマホがどのWiFiをキャッチするかで、受信状況が変わってくるというイメージ。
しかも、自分のスマホは、より強いWiFiを受信する傾向にあるので、飛び交っているWiFiがどんなものかによって大きく影響を受ける。
高校野球の甲子園常連校は、いわば「野球が強いWiFI」が指導者からも選手からも全体に発信されているので、新しく入った部員もその影響をビンビンと受けているはず。
勿論、個人の努力は大事だけど、こうした「環境」に身を置くことは何か物事を行うには非常に重要だろう。
特に、強いWiFiを発信する立場の人。親だったり、先生だったり、会社の上司だったり、は特に自分の発信するWiFiに責任を持っており、そのことをしっかり注意することが重要だ。
こうしたことを考えると、自分が努力して実力を身に着けることはもちろん大事なことだが、どんな「環境」で努力を続けるかということはもっと大事かも知れない。
例えは良くないが、非行グループの仲間の中で、一人だけ真面目であることは難しいだろうし、逆に真面目な環境の中であれば、悪い行いも控えようということになるかも知れない。
ただ、注意しなければいけないのは、例えば、大人は転職するなど自分で環境を変えることができるが、子供は自分で出来ない。だから、親の役目は子供の育つ「環境」づくりに責任がある。
人間は「環境」にすぐ慣れてしまう生き物だというし、何か目的を持って生きるのなら、自分が身を置く「環境」についてもっと意識したほうが良いだろう。
良い環境づくり → ウェルビーイングにつながる!!
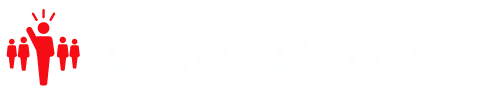



コメント